校長室より
(校長室より) 「主体的に学ぶ」(8/20)
7月、主体的に生きてほしい、という話を生徒たちにしました。8月12日付日本経済新聞の池上彰氏のコーナー「若者たちへ(池上彰の大岡山通信)」で、「主体的に学び、自ら発信」というテーマの記述がありましたので、その一部を紹介します。
「ユニークだったのは授業のあり方に関する発表でした。【主体的に参加するには】【どうすれば面白くできるか】という問題定義がありました。(中略)ある学生は、課題を克服するために【授業で質問しよう】と提案しました。きっかけは【パックン】の愛称で知られるパトリック・ハーラン氏の講義を受講したことです。対話を通じて新たな発見が生まれ、授業が面白くなったといいます。一方的に教えられるのではなく自ら講義に参加してつくっていくこともできます。これぞ大学の学びの姿勢です。」
この文章は、池上氏が数年前から勤めている東京工業大学にて、7月に開かれた教養卒論発表会を取り上げています。池上氏が東工大に着任したころは、学生は自分の考えを人前で伝えたり、他人とコミュニケーションしたりすることが苦手だったようです。この数年で明らかに変わったといいます。
本校においても、「主体的・対話的で深い学び」ができるような授業や実習を目指しています。生徒たちは、主体的に生きることと同時に、主体的に学ぶ手法を身につけ、自ら発信できる力を手にいれてほしいと思います。
(校長室より) 山(8/9)
8月4日付朝日新聞の投書欄のテーマは、「山」でした。「両親に教わったすばらしさ」というタイトルの文章を一部紹介します。
「山好きだった父のおかげで、子供の頃の夏の旅行は、家族で3、4泊の日本アルプスの山歩きだった。(中略)成人してからは、仕事の合間に百名山を目指すほど熱中した。今は子供と日帰りハイキングに行く程度になったが、山のすばらしさを教えてくれた両親には、本当に感謝している。」
私も、毎年夏に登山をしています。富士山や磐梯山、那須岳、燕岳、雲取山、常念岳など、百名山を目指しているわけではありませんが、登山を楽しんでいます。この投稿欄にはこんな文章もありました。
「10年ほど、東京の高尾山に登っている。初めの数年は、夫と一緒に紅葉の頃に登った。きつかったけど、ダイエットに成功したら、楽になった。近年は混雑する前の10月くらいに、一人で行く。目的は体力検査だ。」
登山をする目的は、人によって違います。家族旅行、百名山、体力検査等々、多くの人々が登山を楽しんでいます。何度登っても登山はきついですが、疲れても、疲れても、また登りたくなります。この夏も山に登り、英気を養いたいと思います。
(校長室より) 知らない世界を知ること(8/5)
7月28日付朝日新聞に、「千葉大【全員留学】を義務づけへ」というタイトルの記事が掲載されました。
「来春から千葉大が、入学者全員に【海外留学】を必修とすることを決めた。授業料も値上げする。【全員留学】は一部私立大学や国際系学部では広がりつつあるが、同大によると、国立大が大学院を含め全学で義務づけるのは初めて。」
【全員留学】は、国際教養大(秋田市)や早稲田大国際教養学部など、国際系の新学部や一部私大でも始まっています。ある大学では、新入生の入学式の日に、短期留学できる旅行の準備(荷造り)をさせて、入学式終了後すぐに海外留学に出発させるようです。千葉大学の小沢副学長は、「千葉大が今進めている教育改革の最大の目標はグローバルな社会で生きていける人材を育てること。その環境整備の柱の一つが全員留学です。在学中に最低1度、2週間から2ヶ月間、まずは海外をみて考えてほしい。」と述べています。
本年2月、文部科学省で開催された「トビタテ!留学JAPAN」第4回留学成果発表会を参観してきました。そこでは大学生の他に高校生の発表もありました。彼らは、回りに日本人が誰ひとりいない環境に放りこまれ、言葉の壁に悩み、数日間は挫折を味わいます。しかし、このままでは何も得られないと開きなおり、何がわからないかをホストファミリーや先生や他国の学生達たちに問いながら、少しずつ自分の意見を伝えられるようになっていきます。海外では自分から前にでて積極的に発言しないと、誰も助けてくれないし、何も教えてくれません。語学力や異文化理解力だけでなく、挑戦する力やコミュニケーション力、積極性などを手に入れます。そして何よりも素晴らしいのは、彼らが同年代の海外の若者と交流し協働することで、様々な刺激を受けて将来の夢につなげていくことです。人生には多様な選択肢があることを知るきっかけになります。
留学が難しければ、ボランティアや地域貢献でもかまいません。知らない世界を知ることで、その後の人生に大きな影響を与えるはずです。
多くの高校生、大学生に海外などの未知の世界に飛び出してほしいと思います。
(校長室より) 「7つの習慣」(7/30)
今回は、本の紹介をします。タイトルは「7つの習慣」(ティーンズ)、ショーン・コビー著作です。この本の元になっているものは、スティーブン・R・コビー氏の著作「7つの習慣」で、全世界で販売部数3000万部を記録した本であり、20世紀に最も影響を与えたビジネス書の1位に輝いています。これは、そのビジネス書を、中学生~高校生向けにわかりやすくしたもので、「7つの習慣」を様々な生活シーンの中で取り入れることで、将来に向けた正しい「選択」ができるように書かれたものです。
7つの習慣とは、①主体的になる、②終わりを考えてから始める、③一番大切なことを優先する、④Win-Winを考える、⑤まず相手を理解してから、次に理解される、⑥シナジーを創り出す(チームで協働して結果を出す)、⑦自分を磨く、となります。これら一つ一つについて、自分、親、友達、学校の先生等、それぞれと関わる場面を具体的にふれながら説明がなされます。今回は、この本で指摘されている2つの視点を紹介します。
1つ目は、自己信頼口座(残高)という視点です。これは、第1の習慣に入る前に、私的成功を勝ちとる方法として紹介されています。自分自身を信頼するために何をすればいいのでしょうか。①自分に約束したことを守る、②小さな親切をする、③自分に優しくなる、④正直になる、⑤自分を再新再生する(自らをリフレッシュし、生まれ変わらせる)、⑥自分の才能を開発する、これらを実行すれば自分自身への信頼残高を増やすことができます。ちなみにこの残高を減らす行為は、自分に約束したことを破る、内にこもる、自分を痛めつける、嘘をつく、自分をすり減らす、自分の才能をないがしろにする、となります。
2つ目は、人間関係信頼口座(残高)という視点です。これは、第4の習慣に入る前に、公的成功を勝ち取る方法として紹介されています。他人からの信頼を得るために何をすればいいのでしょうか。①約束を守る、②小さな親切、③誠実、④人の話に耳を傾ける、⑤謝る、⑥見通しをはっきりさせる、これらを積み重ねれば、信頼を得ることができます。他人からの信頼を失う行為は、約束を破る、人と関わらない、うわさ話と裏切り、人の話をきかない、横柄な態度をとる、物事をうやむやにする、となります。
多くの中学生、高校生に本書を読んでほしいと思います。
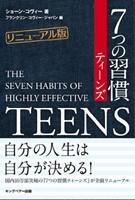
(校長室より) 「主体的に生きる」(7/23)
7月19日(金)1学期終業式にて、私から2点ほど生徒に話をしました。
1つめは、命と時間の話です。私は、本年1月、前任校に勤務していましたが、ある朝、小学部の児童が自宅で亡くなりました。朝、お母さんが気づいた時にはすでに亡くなっていたそうです。彼女は障害をもっていましたが、1~2学期はほとんど休まず元気に学校に登校していました。学校が大好きでした。彼女の人生は11年間でした。時間にすると約10万時間です。みなさんがもっている命(時間)は、あと何時間ありますか? たとえば、明日、命を失うと仮定すると、残りの人生はあと24時間程度です。30日後に命を失うと仮定すると、720時間ありますが、3分の1は寝ていますからあと480時間程度です。平均寿命というのがありますが、あくまで平均なので、みなさんがもっている残りの時間は誰にもわかりません。そして死ぬまでの時間は確実に減っていきます。時間を無駄に過ごすことは、命を無駄にすることと同じです。3年生は進路実現のため、夏休み39日間、1日1日が重要な時間となりますが、同様に1・2年生にとっても時間(命)を大切に使ってほしいと思います。
2つ目は、主体的に生きてほしいということです。この言葉は言い換えると、自分の道は自分で決めて生きる、ということです。あなたの未来は、誰が決めるのでしょうか。友達、両親、学校の先生でしょうか。自分の進むべき方向が明確でないと、まわりの人と同じような選択をすることが多くなります。まわりの人が正しい行き先を知っているのでしょうか? 先のことなんて、誰にもわかりません。人と同じことをやっても、あなたに合う保証はありません。20歳のとき、30歳のとき、どんな未来が待っているかなんて、誰にもわからない。だから、どの道が自分にとって一番いいか、自分で判断して、自分の道を決めてほしい。もし決まっていなければ、この夏、徹底的に考えてください。残された時間は限られています。残された時間は、確実に減っていきます。限られた命、限られた時間を大切にして、自分の進むべき道を考えてほしいと思います。



